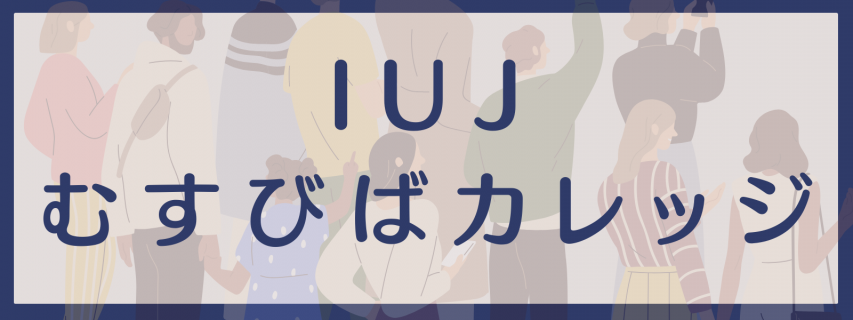IUJむすびばカレッジ Q&Aコーナー
ご回答:シニアンスカヤ ユリア (国際関係学研究科在学 2年生)
| ・ロシアは北朝鮮が重要ですか? |
はい、北朝鮮は東アジア地域の勢力均衡や朝鮮半島への影響力維持にとって重要であるだけでなく、現時点ではロシアにとって重要な戦略的軍事パートナーでもあります。
| ・ プーチンの25年で生活が豊かになったとありましたが、他国への出稼ぎなどはありますか? |
最近は、旧独立共和国、特にタジキスタンとウズベキスタンからロシアへ出稼ぎに来る人が増えています。かつてはウクライナやアルメニアからも労働移民が来ていました。また、小さな町から大きな町へ移住する人も増えています。
現代の問題として、高度なIT専門家がロシアを去ってしまう可能性が挙げられます。政府は、彼らをロシアに留まらせるためのプログラムを展開しています。
もう一つの問題は、政財界のエリート層を含むエリート層の子弟が海外留学していたことです。しかし現在、国内の教育機関の評価を高めることで、この状況を変えようとしています。
ご回答:竹内 明弘 (国際大学言語教育研究センター 日本語プログラム 特任教授)
| ・「日本語における助詞の選択について相違はありますか??」 -昨日東京に行った -昨日東京へ行った |
日本語教育の観点からは(目的地)助詞の後の動詞が「行く、来る、帰る」
なら助詞は「に」でも「へ」でもいい。
(存在する場所)助詞「いる/ある」では、「に」しかとれません。
例:〇そこに幽霊がいる/PCがある。✖そこへ幽霊がいる/PCがある。
名詞句を作る場合、〇「長友選手へのメール」は言えるのに対し、✖「長友選手にのメール」とは言えません。
国語としての立場では厳密に言うと、「に」は目的地、「へ」は移動の方向を表すとされており、
「ごみはゴミ箱に」はゴミ箱が目的地なので、そこに正確に入れることを意味しますが、「ごみはゴミ箱へ」
というとゴミをごみ箱に向かって投げれば、入らなくてもOKということになります。
ご回答:ニシャンジ エブル(国際関係学研究科在学 2年生)
| ・トルコ料理は世界三大料理の一つですが、日本ではあまり食べる機会がありません。一番好きなトルコ料理を教えてください。 |
私が一番好きなトルコ料理はラフマジュンという料理です。薄い生地の上にお肉や野菜をのせて焼いたトルコ風のピザで、レモンを絞って食べるのが特徴です。日本ではあまり知られていませんが、とてもさっぱりして食べやすい料理です。
| ・ なぜ日本の大学を選ばれたのか。 |
日本の大学を選んだ理由は、学問だけでなく文化や生活も含めて幅広く学べると思ったからです。日本社会の仕組みや価値観を現地で体験することで、自分の視野を広げたいと考えました。
-----------------------------------------------
ご回答:石原 由佳 (国際大学 国際社会起業家プログラム在学生(当時))
| ・国の不平等などをなくすために、どのような活動をすればよいのか。 |
青年海外協力隊に挑戦してみてはいかがでしょうか!….というのは大きな決断になるかもしれませんが、普段の生活の中でもいろいろなことができるように思います。例えば私が日本にいるときは、不平等なシステムの中で作られたものはなるべく買わないように、値段や生産国を気にかけて買い物をするようにしています。もちろんそういったものを買うこともありますが、そしたらなるべく大切に使うようにしています。
| ・海外に行かれて、日本のデザインを見た時にどう感じましたか。 |
日本のデザインは余分な部分がなく、シンプルで、かつユーザーフレンドリーだと感じます。デザインしている人が、使う人のことをよく考えているなと思って感心します。でもそれが他の国より優れている、とは思っていなくて、それぞれ違う魅力があると感じます。例えば海外に行くと、なんだか余計なものがたくさんついていてごちゃごちゃで使いにくいのに、なぜか魅力があるデザイン、というのも存在するのですよね…面白いものです。
| ・10月に海外で、英語でプレゼンテーションを行います。できればその方法を教えてほしいです。 |
わたしも修行中です。英語でプレゼンするときは、いつも大体のスクリプトを書いて、何回も練習しています。難しいですよね。10月のプレゼンテーション、頑張ってください!
ご回答:松山 良一 (学校法人 国際大学理事 兼 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM) 所長 /
元・⽇本政府観光局 (JNTO)理事長)
| ・観光に力を入れることにより、地域の特性はどう変われるのか。観光客と若者、年寄りそれぞれの住みやすさは変わるのか。 |
観光に力は、①外国人と草の根レベルの相互理解が深まる ②雇用増、外貨獲得に貢献する ③地方創生の切り札 ④地域価値の再発見 にあります。この観光の力をどのように生かすかは、地域の皆様自身が、どのような地域を目指すかの総意づくりがまず重要です。高山、白馬などの先進事例を学び、南魚沼にどのように生かすかですが、この段階では地域を取りまとめるリーダーが必須です。
| ・日本人のアイデンティティ、良いところを残しつつ、世界標準の価値観に切り替えていくのか、その方策はないのか。 |
日本人のアイデンティティを世界標準に切り替える必要はないと思います。日本人のアイデンティティに自信と誇りを待ち、外国の違う価値観を尊重し、相互理解を深める努力が必要と思います。
-----------------------------------------------
ご回答:野崎由紀子(学校法人国際大学 評議員/IUJ修了生)
| ・カースト制度や男女差別の弊害が経済発展に及ぼす影響 |
| ・粗鋼生産量はどうなっているのですか、アメリカUSスチールのニュースで気になりました。 |
2047年までに先進国入りすることを目指し、国内インフラ建設を急ピッチで進めています。そうした国内の建設需要の高まりという背景に加え、「自立したインド」をスローガンとしたメイク・イン・インディア政策も相まって、国内の粗鋼生産は拡大していると理解しています。
| ・インドにおける社会福祉の状況、例えば貧困者たちの状況など |
貧困対策としては、政府の施策として昔から食料の公的分配システム(配給制度)がありますし、最近では、低所得者向け住宅の提供なども政策の目玉の1つとして掲げられています。民間レベルでは、ヒンドゥスタン・ユニリーバによる農村部の貧困女性支援のためのシャクティに代表されるソーシャルビジネスや、講演でお話したようなフリースクールなどボランティア団体の活動が活発な印象です。
| ・What do you think about Indians in Japan. Do you believe its easy or hard fo them to adapt compared to a japanese person adapting in india? |
日本にいるインド人留学生の数は非常に少なく、日印の人的交流をもっと増やすべきです。日本人がインドでゼロから英語やヒンディ語を習得するのはかなりの時間を要しますが、インド人が日本語を習得するのは早く、日本人がインドに適用するよりも容易にインド人は日本に適用できると思います。
| 先月の加藤先生はじめ、多くの先生方の講演(勉強会)をもっとお聞きしたいときは、どんな方法がありますか |
ありがとうございます。5月24日(土)に開催されるインターナショナルフェスティバルにて加藤副学長による公開授業がございます。
英語での講義ですが、どなたでも自由にご参加いただける機会となっております。詳細はこちらからご確認ください。
日時:5月24日(土) 13:00~14:00
開場:国際大学 203教室
(回答:むすびばカレッジ運営事務局)
ご回答:加藤 宏 副学長/教授
| ・食糧の増産の可能性、何か育てやすい作物はあるのでしょうか |
お話しの中でも話しましたが、アフリカでは穀物の生産性が低く、生産量も足りていないので、大陸全体としては穀物を輸入している状況です。これには複雑な背景があります。一つには、植民地時代からの影響が今も残る「換金作物」(コーヒー、カカオ、お茶など)重視の農業政策がありますし、加えて、伝統的に農業を重視してこなかった各国の政策の「つけ」が回ってきているということもあります。
アフリカでの食糧増産の余地があるものとして日本政府が着目しているのは「米」です。アフリカではコメの消費が増えつつあり、それに伴って輸入も増えていますが、他方、日本や他のアジア諸国に比べて単位面積当たりの収量がまだ低いのです。しかし、アフリカでも、アジア式の生産技術を導入すれば生産性が上がり、増産も可能だということがこれまでの協力を通じてわかってきました。そのような成果を踏まえて、とりあえず、2030年までの期間を見据えて現在も協力が進められています。なお、蛇足ですが、アフリカの米の増産を支援しても日本の農家さんへの脅威にはなりませんので心配もいりません。
ご回答:アルワ・ハルガさん
| ・アニメでどうやって日本語を学ぶのか、その具体的な方法 |
②覚えたフレーズを実生活で使うようにしました。アラビア語や英語ではなく、日本語で話すことを心がけました。1年以上続けることで、多くのフレーズを自然に覚えることができました。
③その後、日本のアニメソングを聞いたり、YouTubeでひらがな・カタカナの動画を見たりしました。ここで初めてノートを取り、実際にペンを持って書く練習をしました。
④さらに、「しゃべくり007」や「VS嵐」などの日本のバラエティ番組を見るようになりました。漢字の勉強にもなると思ったからです(この時もノートは取りませんでした)。番組内の会話を理解することで、画面に表示される漢字がその単語の書き方だと気づきました。その結果、たくさんの単語を覚えましたが、漢字の書き方は分からないままでした。
⑤最後に、日本のドラマを見て、日本人のボディランゲージを学び、より自然な日本語を身につけようとしました(現在も継続中です)。
(補足)
ほとんどノートを取らなかった理由は、繰り返し視聴することのほうが、ノートを見返すより効果的だと感じたからです。また、ノートを取ることで「完璧にしなければならない」というプレッシャーを感じ、学ぶことが楽しくなくなってしまいました。言語はコミュニケーションの手段であり、完璧を目指す必要はありません。人はどんな言語でも完璧にはなれません。だからこそ、楽しみながら学ぶことが大切だと思います。
| ・日本人と海外の方が関わる際にいいイベントの内容はありますか? |
浦佐駅には多くのイベントポスターが掲示されています。これらのイベントはとても魅力的で、学生にとって日本を知る良い機会ですが、すべて日本語(特に難しい漢字)で書かれているため、理解が難しいです。英訳を追加することで、学生がより関心を持ち、参加しやすくなると思います。
②ボランティア活動の促進
多くの学生はキャリア志向が強く、履歴書に「〇〇でボランティアをした」と書けることを重視しています。高齢者支援や街の清掃など、地域に貢献できるボランティア活動を提供すれば、学生も積極的に参加しやすくなるでしょう。
-----------------------------------------------
ご回答:櫻井 美穂子准教授
| ・とにかく生活に直な話で大変勉強になりましたが、これはどうゆう「学問/分野」ですか? |
フェーズフリーについては決まった学問分野が存在するわけではありませんが、防災教育、建築、社会学など様々な背景を持った専門家が携わっています。私自身は講演の最後にご紹介したようなデジタル活用やレジリエンスを研究しており、経営情報システムという学問領域から関わっています。
≪第18回≫ 2024年9月21日(土) テーマ 「「ポスト地⽅創⽣」のまちづくりを考える-移住定住・関係⼈⼝・地域のつながりに着⽬して-」
ご回答:伊藤 将人研究員/講師
| ・各地方そのものが、どれだけ郷土愛、またはアイデンティティを育む取組、方向づけをしているのだろうか。 |
各地域による郷土愛、またはアイデンティティを育む取り組みの実態は多様であり、地域差があるのが実態です。ただいくつかの研究で明らかになっているのは、小学校から中学校、そして高校における郷土学習や地域をフィールドとした探究学習は、郷土愛を育んだり、移住Uターン志向の構築に一定程度寄与しているということです。そこで重要となってくるのは、ただ楽しいだけの学びや、受け身の学びではなく、実際に地域の人と触れ合い、何かしら地域に貢献する取り組みを行うことで、「地域の役に立った」「地域に僕は、私は必要とされているんだ」と感じる機会をたくさん設けることです。こうした経験は、シビック・プライド、つまり郷土愛やアイデンティティを育むことにもつながるでしょう。南魚沼市でもこうした取り組みは行われていると思いますが、所属する学校や住む地域によって機会に差があるのではと思います。そうした地域と関わる体験の格差を縮小していくことが、大人の責務と考えています。
| ・前もって質問したのですが。地域における消費が喚起なくして地方創生なんてあり得ない。民間はものが変なものだったら、2度と誰しも買ってくれない。こう言うマインドは残念ながら役所にはない。知恵は、地域や民間にあると思う。どう思いますか。 |
当日、ご挨拶した際にお話した内容と重複しますが地域における消費は非常に重要です。特に地方創生以降、地方の中小企業の取り組みは必ずしも注目を集めてきませんでしたが、今こそ改めて地方の、そして地元の中小企業の価値を再発見し、中小企業が存在することそれだけで地方創生に強く貢献しているという意識を拡大していくことが重要です。行政と民間の違いに関してもご指摘のとおりですが、一方で行政には行政にしかできないこと、逆に行政が踏み込んではいけない領域があります。近年は、行政にもマーケティング思考や経営思考の拡大が求められていますが、それは重要であると同時に、行政はマーケティングや経営といった枠組みを超えた「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する. 役割を広く担う」存在です。換言すれば、損得やメリット・デメリットを超えて、地域住民の福祉の増進、そこには人権や公平さなどが含まれますが、こうしたことにしっかりと目を向けられているのか、民間的思考に侵されすぎてはいないかも同時に考えるときが来ているように思います。また、行政職員と言っても、結局はその多くが地域住民でもあります。官僚制の限界の中で、個人としてはこの地域をどうにかしたいという思いを持った行政職員もたくさんいるでしょう。そういった人も巻き込みながら、垣根を超えて協働していくことが求められていると思います。
-----------------------------------------------
≪第15回≫ 2024年5月18日(土) テーマ「蔓延するフェイク情報の実態と私たちができる対策」
ご回答:山口 真一准教授
| ・フェイクニュースを信じている方をどう正すのか、方法論、議論の方法について。 |
ご質問いただきありがとうございます。非常に難しい質問です。私がよく申し上げているのは、フェイクやファンタジーを信じる自由もあるので、「それが同僚程度の距離感の場合は、そういう考え方もあるかと思ってスルーする」ということを推奨しています。しかし、家族等非常に身近な存在で、かつ、その人がフェイクを強固に信じていて何かを強要してくる場合には、実害が出るので是正する必要があると思います。その場合は、頭ごなしに否定するのではなく、丁寧なコミュニケーションを根気よくしていくことが重要です。話をよく聞いていく中で、少しずつ科学的・客観的な観点から別の視点を提示し、フェイク情報を信じている人が自ら気づいていくようにしていくことが大切です。数か月~1年かかるようなこともありますが、根気よく続けていくことが解決につながります。
≪第14回≫ 2024年4月20日(土) テーマ「ベトナムにおける日系企業のサステナビリティ戦略について考える」
ご回答:レ タン フーさん
| ・ベトナムの若者がサステナビリティに興味がある理由を教えてください。 |
その理由としては、若者がSNSを通じて環境問題やサステイナビリティについて考える機会が増えてきたからです。ベトナムには世界各国から労働力や生産量を求めて工場が集まっています。しかし、大気汚染の問題が深刻な街としてハノイが1位、ホーチミンが3位にランクインしてしまいました。その後、「Go Green」というキャッチコピーがSNSを介して拡散し、若者の間で環境問題に関する意識が高まりました。
| ・(環境のためには)あまり経済が発展しないほうが良いのでは?農業を大切に、地球を大切に。ご意見がありましたら教えてください。 |
≪第13回≫ 2024年3月16日(土) テーマ「稲作、信頼と経済発展」
ご回答:後藤 英明教授
| ・今後の日本という国のことについて先生のお考え |
難しいご質問です。個人的には、技術革新の活用等によってどれだけ労働生産性が向上していくか、また、生活の質を高めるためにどのような取り組みが可能か(なされるか)、といった点に注目しています。
| ・政治制度の経済発展が及ぼす影響 |
経済発展が政治制度にどのような影響を与えるかは、各国の歴史的背景、文化や慣習、教育水準、経済構造(たとえば、どのような分野・産業による経済発展か)等々、数多くの要因に依存しますので、特定の国にご関心がある場合はその国の事例を詳細に考察する必要があり、私の手には余ります。ただ、経済成長と民主主義の関係を分析したマサチューセッツ工科大学のアセモグル教授らによる研究によりますと、民主主義は経済成長に寄与する傾向がありますが、経済成長は必ずしも民主主義を促進するとは限らないようです。
| ・インドはこれから発展すると言われていますが、先生の資料をみると難しそうですか? |
私はインドの専門家ではありませんが、経済発展は忍耐強さ、信頼、個人主義・集団主義といった(文化的)要素だけで決まるものではなく、教育、制度、インフラ等々、多くの要因が絡み合っています。文化的特性も重要ですが、それだけが全てではなく、多様な要素を総合的に考える必要があると思います。
-----------------------------------------------
≪第12回≫ 2024年2月17日(土) テーマ「2024:世界の紛争地帯を俯瞰する」
ご回答:山口 昇教授
| ・私たち、日本人、一市民として、世界平和に貢献していく為に、具体的にできることは何か、教えてください。 |
私たち一人一人の立場できちんと責任を果たしていくことに尽きるように思います。そのためには、ご自分の立場に誇りを持ち、かつ他人の立場にも敬意を払って、より良く、より豊かな社会を築くことが第一のように思います。
| ・世界の安定(戦争)について |
歴史は神(あるいは仏)が司どるもののように思えてなりません。謙虚に神仏の思し召しだということを認めた上で、平和と安定のために人類ができることを最大限積み重ねていくということでしょうか?
| ・日本の国防をどうしていくのが重要か |
国が生存し続けるためには国防が不可欠ですが、国防が目につかない平和な状態が最も望ましいことにも注目すべきだと思います。その上で、平和とは何かを考える際、平和でない状態をイメージアップし、それを避けるために何をするかという問いに正面から取り組むことも時折必要だと思います。
| ・羽田事故について関係者全体に無いものは異常事態に音で注意喚起するなり、全体移動等をさせるようなシステムが必要と思いますか?目だけはダメです。 |
航空事故の多くは、何重にも施された安全策を「偶然」すり抜けて起きます。手痛い経験を無駄にすることなく、対策を積み重ねていくことが不可欠で、その中には、機械やシステムによるものだけでなく、運航に関わる人々の意識を良い方向に向けるた目の施策も必要です。
| ・憲法改正についてのお考え、第9条など。 |
9条にこだわらず、改正の手続きを経ることで「日本国憲法は自分のものだ!」という意識を強めることができるのではないかと期待しています。前文にある「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う」という部分は特に好きですが、終戦直後の占領下で制定されたこともあり、なんとなく自分のものではないような気持ちがあるのではないかと思います。自分たちの憲法に誇りを持つためにも、議論を深めることは有益ではないでしょうか?
====================================
お問い合わせ:
国際大学むすびばカレッジ事務局
Eメール:presoff@iuj.ac.jp
電話:025-779-1486
====================================